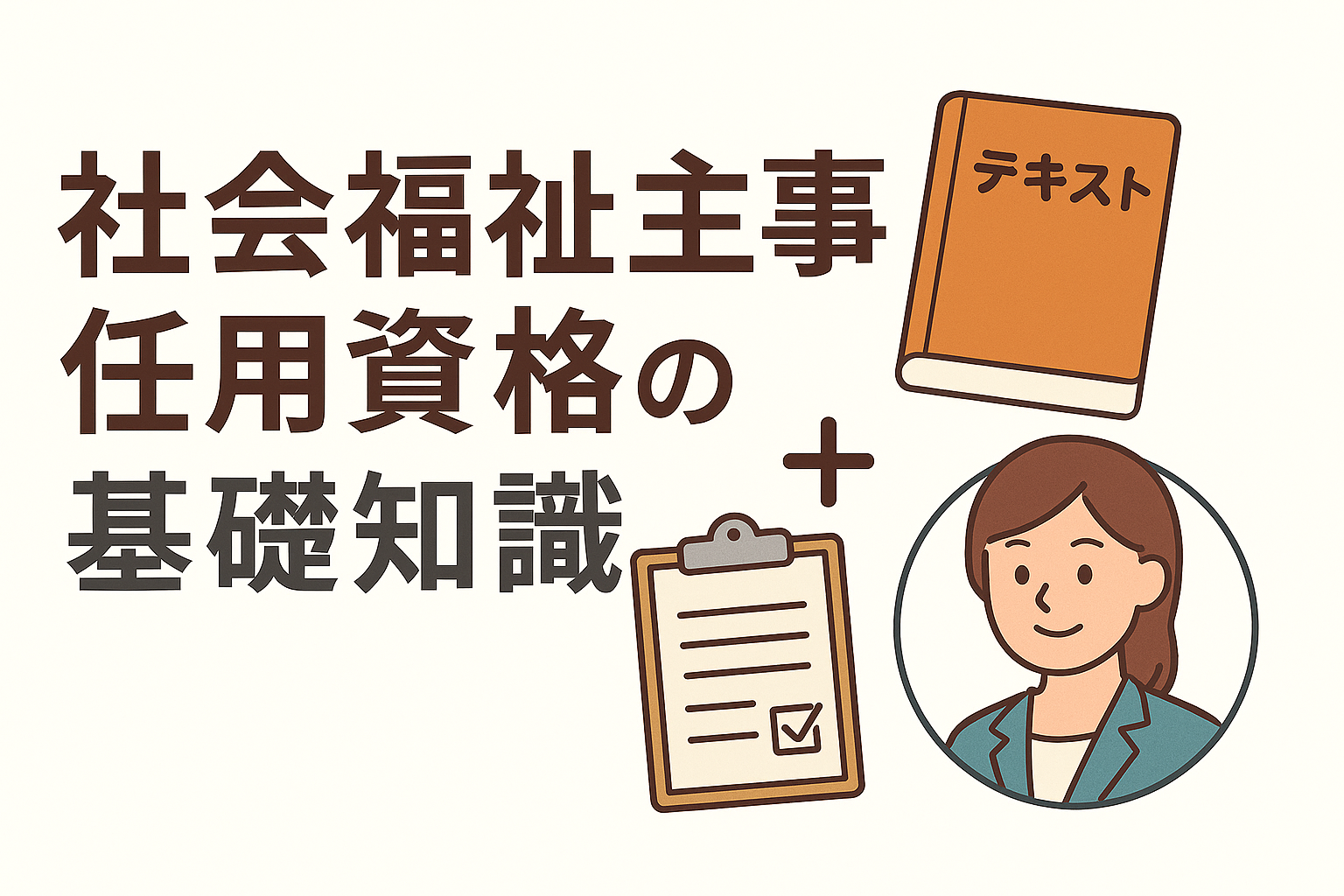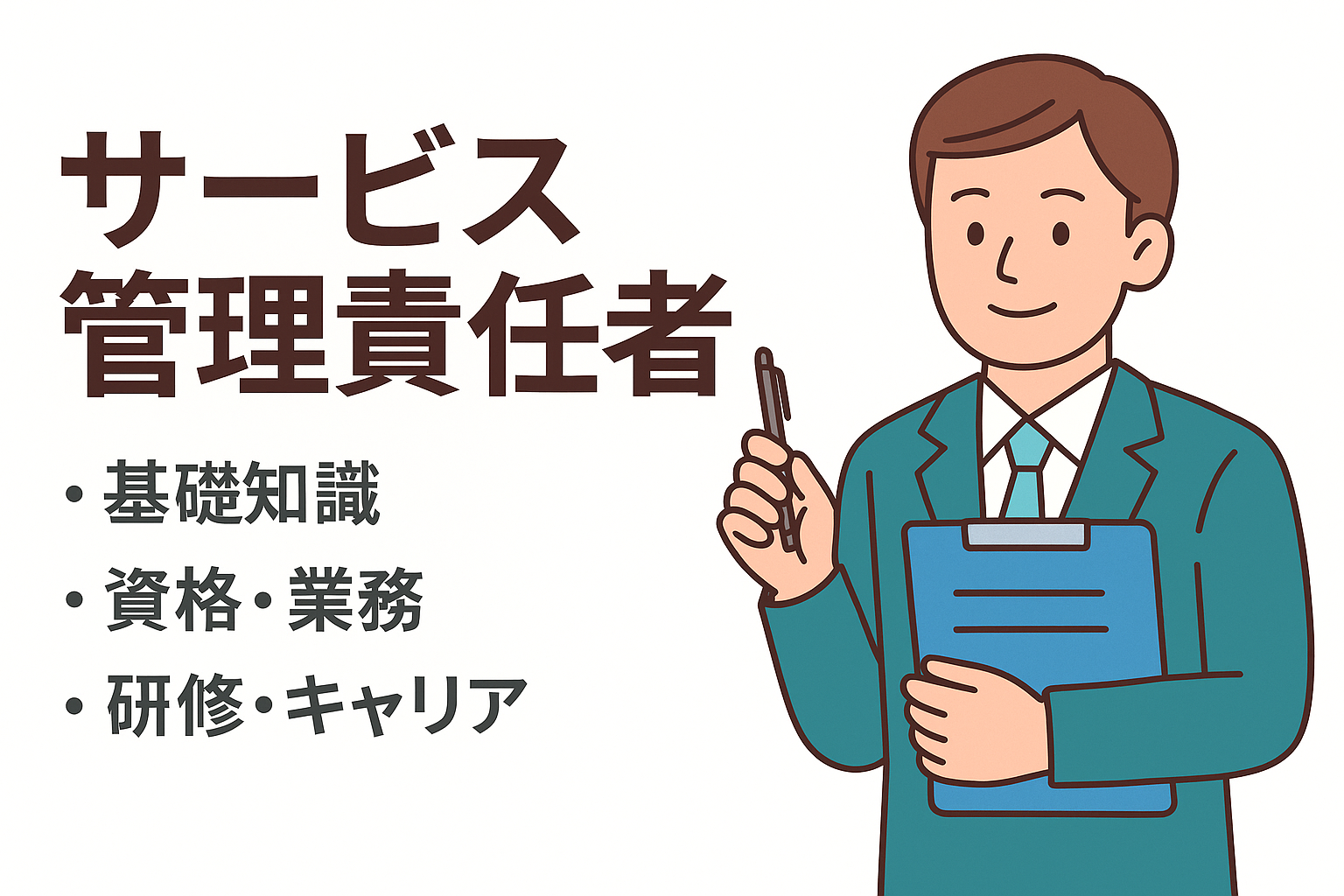児童福祉司は、児童相談所に勤務して、子どもや家庭の問題に対応する専門職です。児童虐待や非行、障害、育児放棄など、多岐にわたる問題に対して、相談や調査、指導、援助を行います。子どもたちの福祉と権利を守るために、法律的な判断や心理的なケア、保護措置の判断など、高度な専門性が求められる仕事です。
そのため、児童福祉司になるには、法律・福祉・心理などの分野に関する知識を身につけた上で、「児童福祉司任用資格」を有することが前提となっています。
活躍の場
児童福祉司は、主に都道府県や指定都市が設置する児童相談所に配置されます。厚生労働省のガイドラインによれば、児童福祉司の配置基準は、管轄人口4万人に対して1人が目安とされています。
その業務は多岐にわたり、下記のような事案に対応しています。
- 虐待の通報や相談対応
- 一時保護や施設入所の判断
- 保護者との面談・指導
- 他機関(学校、医療機関、警察など)との連携
- 里親支援や家庭復帰の調整
特に近年は児童虐待の通報件数が増加しており、現場での判断力とチーム連携が重視されています。
資格の取り方
「児童福祉司任用資格」は国家資格ではなく、都道府県・市町村等が「任用」する際に必要な「任用資格」です。
以下のいずれかに該当すれば、任用資格を有するとされます。
主な任用資格の取得方法
- 大学や短大で指定科目を修めて卒業
福祉・心理・教育・社会学・法学などの学部で、必要な指定科目を履修・卒業した者。 - 社会福祉士、精神保健福祉士の資格保持者
- 厚生労働大臣指定の児童福祉司養成機関で所定の課程を修了した者
- 児童福祉業務に5年以上従事した実務経験者
また、上記のいずれかを満たしたうえで、自治体の職員採用試験などを受け、児童相談所に任用されることで、正式に児童福祉司として働くことができます。
指定科目の内容(例)
大学等で任用資格を得るには、以下のような科目を履修する必要があります(大学により名称や科目数に違いがあります)。
| 領域 | 主な科目例 |
|---|---|
| 福祉関連 | 社会福祉学、児童福祉論、社会保障論など |
| 心理関連 | 発達心理学、臨床心理学、心理アセスメント |
| 教育関連 | 教育原理、教育心理学、特別支援教育など |
| 法律関連 | 児童福祉法、民法、刑法、少年法など |
| 医療・保健 | 小児保健学、精神医学、保健学など |
指定科目の内容は変動することがあるため、受験先や志望自治体の要項を確認するのがよいと思います。
児童福祉司の仕事の実際
児童福祉司は、単なる「相談員」ではありません。家庭訪問や施設調査など、現場に出向いて実態を確認し、子どもの安全確保に関わる判断を行います。
必要に応じて児童相談所内でケース会議を開いたり、弁護士や医師と協議を行ったりする場面もあります。
また、子ども本人と関係を築き、信頼される存在になることも重要です。保護者との関係構築も同様で、継続的な支援を通じて家庭再統合などを目指します。
任用後のキャリアと資格
児童福祉司として一定の実務経験を積んだ後は、以下のようなキャリアアップの道もあります。
- 児童福祉施設長
- 主任児童福祉司
- ケースワーカーの指導・監督者
また、さらなる知識を深めるために、社会福祉士や臨床心理士などの資格を取得する人もいらっしゃるようです。