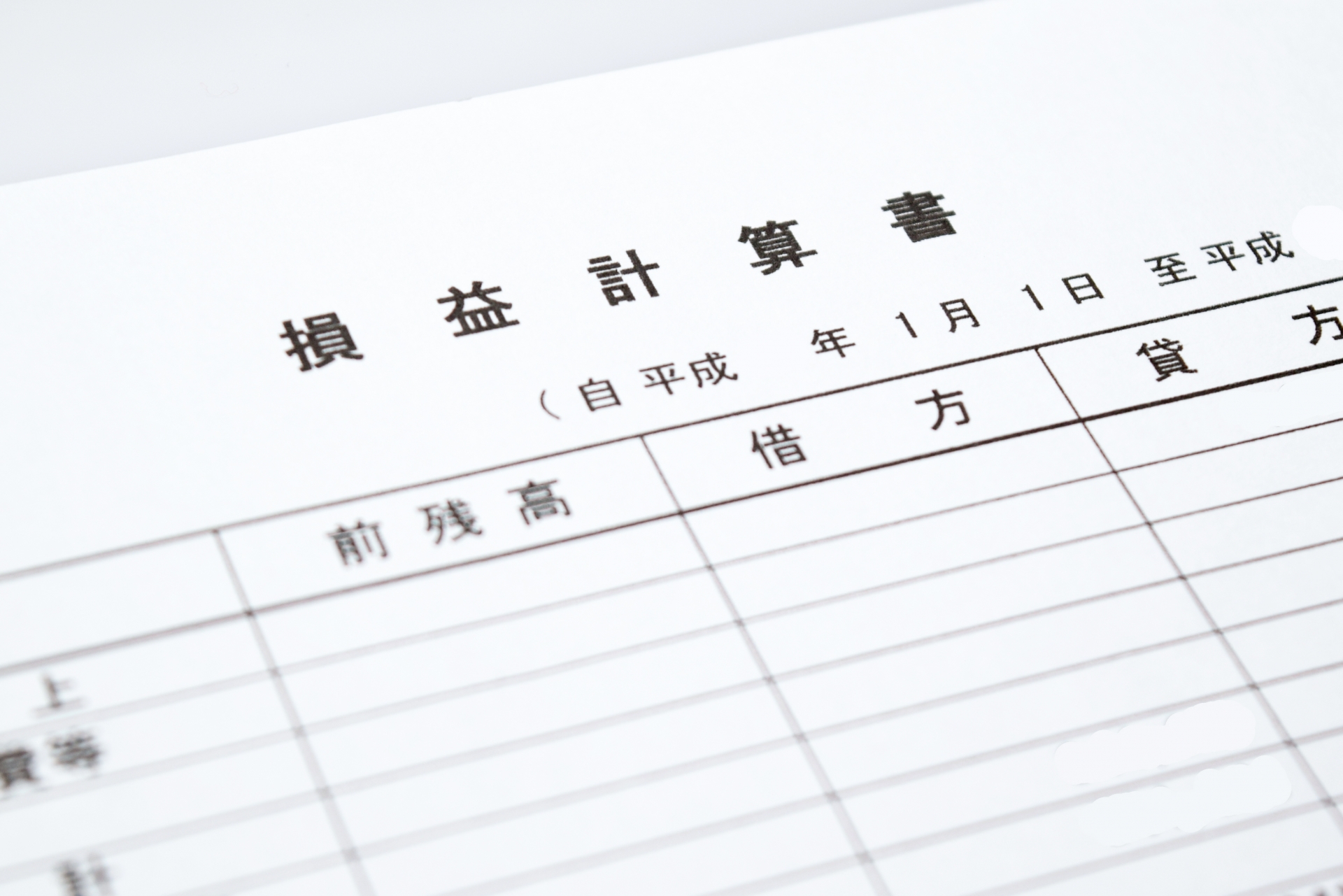住宅資金として準備しておきたい金額としては、頭金として物件価格の20~30%程度が目安と言われます。手続費用や登記に関する諸費用(印紙税、不動産取得税、登録免許税など)、家具の購入や引越し費用まで経費として考えておく必要があります。
2000万円の物件なら、400~600万円ほどを自己資金として用意するのが望ましい計算となります。
財形住宅貯蓄(住宅財形)
自己資金準備のための積立制度です。
| 非課税枠 | 財形年金貯蓄と合わせて元本合計550万円までの利子 |
| 対象者 | 契約申込時の年齢が55歳未満の勤労者が利用できる |
| 契約数 | 一人につき一契約 |
| 積立の目的 | 自己の居住用住宅の取得や増改築のための費用であること。 (目的外に使用した場合は課税される) |
| 積立期間 | 原則5年以上。 (住宅の購入資金の場合は5年以内でも引き出し可能) |
住宅ローン
住宅ローンの金利
金利には「固定金利型」「変動金利型」「固定金利選択型」の3種類があり、融資を受けた時点での金利が適用されます。
| 固定金利型 | ローンを組んだ時点での金利が返済終了時まで変わらない ※金利が低いときに有利なタイプ |
| 変動金利型 | 市場金利の変動に応じて借入金利も変動する 通常、金利は半年に一度見直し、返済額は5年毎に見直し ※金利が低いときには有利で、金利が上がると不利になるタイプ |
| 固定金利選択型 | 当初の一定期間(2年や5年など)だけ金利が固定される 固定期間終了後、その時点での金利で固定金利選択型か変動金利型かを再選択 ※固定金利期間が長いほど金利は高くなる |
住宅ローンの返済方法
ローンの返済方法には「元利均等返済」と「元金均等返済」があります。借入金額、借入金利、返済期間等の条件が同じ場合、返済総額は元金均等返済のほうが少なくなります。
| 元利均等返済 | 毎回の返済額(元金と利息の合計)を一定とする返済方法。 ※返済当初は利息部分の割合が多い |
| 元金均等返済 | 毎回の返済額のうち、元金部分の返済額を一定とする返済方法 利息は元金の残高で計算 ※期間の経過とともに元金残高が減る分利息も少なくなっていく |
住宅ローンの種類と内容
住宅ローンは公的融資と民間融資があります。公的融資には財形住宅融資や各自治体の融資、民間融資は金融機関によるもので物件に対する規制や基準が公的融資よりも緩やかなものがあります。
財形住宅融資
財形貯蓄(一般財形・年金財形・住宅財形)を行っている者が対象です。個人に対する融資ですので、夫婦別々に申し込むこともできます。
| 融資対象 | 1年以上の財形貯蓄をし、残高が50万円以上 原則、申込時の年齢が70歳未満 |
| 融資額 | 財形貯蓄残高の10倍以内(最高4000万円) 住宅購入価格またはリフォーム費の90%以内の金額 |
| 金利 | 5年固定金利(5年経過ごとに見直し) |
| 収入基準 | 住宅ローンなどの返済総額の合計(総返済負担率)が年収の一定割合以下 ・年収400万円未満 30%以下 ・年収400万円以上 35%以下 |
| 保証料・保証人 | 不要 |
| 返済期間 | 最長35年(完済時年齢は80歳まで) |
フラット35
住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して行う証券化ローンです。
| 融資の主体 | 民間金融機関 ※融資後は、住宅金融支援機構がローン債権を買い取る |
| 融資対象 | 本人や親族の居住用新築住宅の建設・購入資金 ※購入物件価格の上限なし ※耐久性などの条件を満たす中古住宅の購入資金も可 床面積:戸建て70㎡以上、マンション30㎡以上、店舗併用住宅は住宅部分の床面積が全体の2分の1以上 |
| 融資金額 | 最高8000万円(購入価格の100%以内) |
| 金利 | 長期固定金利 ※融資実行時点の金利適用 ※取扱金融機関で異なる ※借入期間が20年以下か21年以上かで異なる ※融資率(借入額÷購入価額)が90%を超えると金利が高くなる |
| 収入基準 | 総返済負担率が、年収の一定割合以下であること |
| 保証料・保証人 | 不要 |
| 返済期間 | 15年以上35年以内(完済時年齢は80歳まで) |
| 返済方法 | 元利均等返済と元金均等返済の選択制 |
| 申込時の年齢 | 原則、70歳未満 |
| 繰り上げ返済 | 最低繰上げ額 ・金融機関窓口の場合:100万円以上 ・インターネット(住・My・Note)の場合:10万円以上 手数料不要 |
住宅ローンの借り換えについて
返済中の住宅ローンを別の金融機関の低金利のローンに切り替えて、利息の負担をより少なくしていくこともできます。借り換えの際にはいくつかの注意事項があります。
- 原則として公的融資への借り換えはできません。
一般の住宅ローンからフラット35への借り換えは可能です。 - 借り換えの際には保証料や登録免許税などの諸経費がかかります。
- 有効な借り換えの目安として以下のような数値が一般的です。
- 金利差1%以上
- 残りの返済期間10年以上
- 残債1,000万円以上
住宅ローンの繰上げ返済について
毎月決められた返済額以外に、まとまった金額を追加で支払って、ローンの残高の一部または全額を返済することもできます。返済した元金への利息がかからなくなるので、利息の負担を軽減できます。
繰り上げ返済には「返済期間短縮型」と「返済額圧縮(軽減)型」があります。
一般に、返済期間短縮型のほうが利息削減効果は大きくなります。
団体信用生命保険について
被保険者を住宅ローンを借りた人、保険金受取人を金融機関にする生命保険です。
ローンを借りている人が死亡したり高度障害になった場合に、ローンの残高分が保険金として金融機関に支払われ、ローンは完済となります。