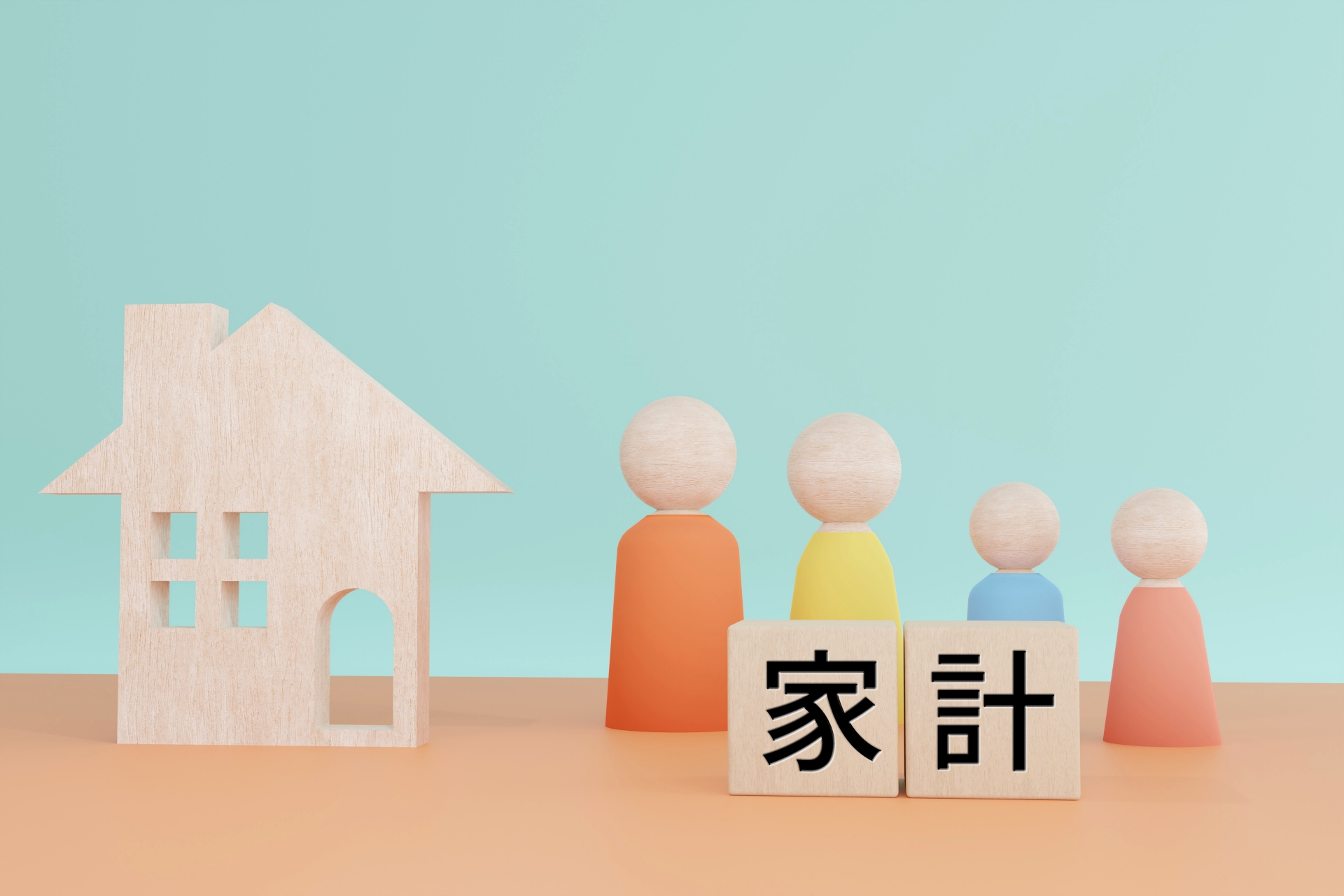家計とは、家庭を単位とした経済活動のことで、主に消費を受け持ちます。職業について働き収入を得て、消費等による支出をまかなっています。収入を多くして、支出をできるだけ抑えることが家計の原則です。
家計の収入
家計の収入には3種類あります。
- 勤労所得(勤労収入):会社・工場・役所などに勤めて、賃金や給料として受け取る雇用者所得のこと。
- 財産所得(財産収入):土地や家屋を貸して得られる地代、家賃、預貯金や公債などの利子、株式の配当など、財産を利用して得られる収入のこと。
- 事業所得(事業収入):個人で事業を経営して得られる個人業主所得のこと。
家計の支出
家計の収入から家庭を維持していくために支払われるものを支出といいます。
- 消費支出:食糧費、住居費、光熱水道費、被服費、教育費、医療費、衛生費・交通通信費・交際費といった、日々の生活の消費に使う支出のこと。
- 非消費支出:国や地方公共団体に納める税金(租税)、国民年金、健康保険、雇用保険などの社会保険費といった、消費以外の支出のこと。
- 貯蓄:収入の一部を生活の安定や将来の供えのために蓄えているもの。銀行や証券会社、保険会社を通して企業や個人の資金、国債、地方債などの財政資金として貸し付けられ、経済活動の活発化にも役立てられている。
- 預金(銀行などの金融機関への貯蓄)
- 貯金(ゆうちょ銀行への貯蓄)
- 株式や国債、社債などの購入
- 民間の生命保険や損害保険への保険料
エンゲルの法則
消費支出のうち、食料費の占める割合(百分率)を表したものをエンゲル係数といいます。
エンゲル係数(%)=食糧費÷消費支出×100
家計の収入が増えるにつれて、このエンゲル係数が小さくなる傾向があることを、エンゲルの法則といいます。
食料費はどこの世帯でもそれほど変わりがないため、収入が少ない家庭ではエンゲル係数が大きくなり、収入が増えるとエンゲル係数は小さくなります。