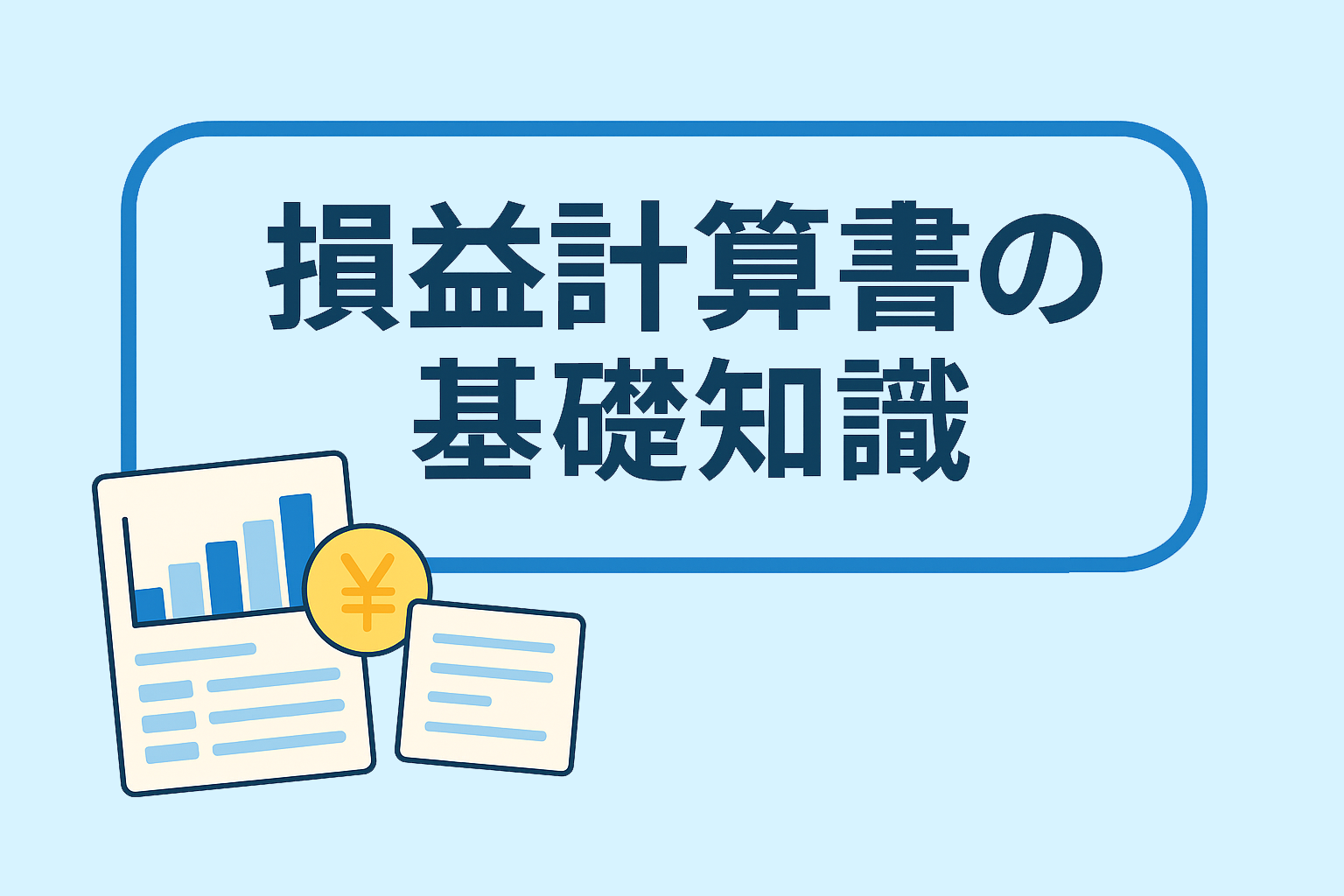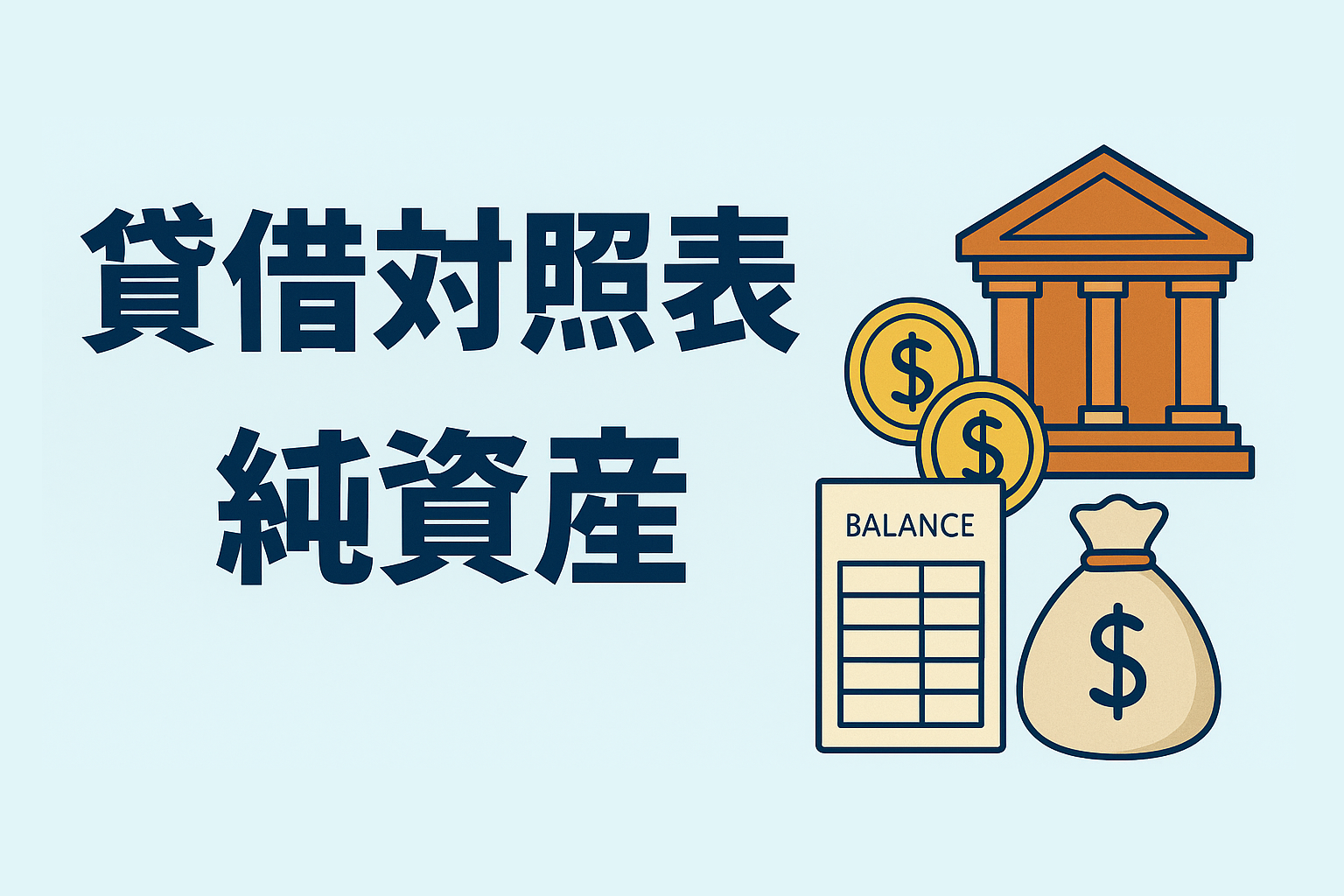損益計算書(Profit and Loss Statement)は、ある一定期間における企業の経営成績を明らかにする財務諸表のひとつです。企業がどれだけの収益を上げ、それに対してどれだけの費用をかけて、最終的にどの程度の利益または損失が発生したのかを示します。
売上高から始まり、売上原価・販売費・管理費・特別損益などを段階的に差し引くことで、営業利益、経常利益、税引前当期純利益、当期純利益といった各種の利益指標が算出されます。
この情報は、投資家・債権者・経営者・従業員などの多くの利害関係者にとって、企業の収益力や収支構造を把握するうえで欠かせない資料となります。
損益計算書の様式
損益計算書には、以下の2つの様式があります。どちらの形式も基本的には同じ内容を含んでいますが、表示の仕方に違いがあります。
報告式
収益と費用を上から順に並べ、計算結果を段階的に下に表示していくスタイルです。企業の開示資料で一般的に使用されています。
売上高
- 売上原価
= 売上総利益
- 販売費及び一般管理費
= 営業利益
+ 営業外収益
- 営業外費用
= 経常利益
+ 特別利益
- 特別損失
= 税引前当期純利益
- 法人税等
= 当期純利益
勘定式
左右に分かれた表で、左側に費用、右側に収益を配置するスタイルです。企業実務ではあまり使われませんが、教育機関や会計の基本学習では利用されることがあります。
損益計算書のルール
損益計算書の作成にあたっては、会計上の基本的な原則に基づいて処理することが求められます。主な原則は次のとおりです。
発生主義の原則
現金の収支ではなく、実際に発生した取引に基づいて収益や費用を計上するという考え方です。たとえば、商品を納品した時点で売上を認識します。
実現主義の原則
収益は、顧客への引き渡しなどにより法的・経済的な義務を果たした時点で計上されるべきとする原則です。契約を結んだだけではなく、成果が「実現」されたことが必要です。
費用収益対応の原則
収益とその収益を得るために発生した費用とを対応させて、同じ会計期間に記載する原則です。これにより、利益が適切に計算されるようになります。
明瞭主義の原則
損益計算書は、多くの利害関係者が読み取る資料です。そのため、以下のような表示ルールが明瞭主義のもとに求められます。
総額主義の原則
収益や費用は、相殺せずにそれぞれの総額で表示する必要があります。たとえば売上高と仕入原価を相殺して純額で記載してはいけません。
費用収益の対応表示
売上原価と売上高、販売費と営業収益など、対応する収益と費用を並べて表示することで、費用と収益の関係性が把握しやすくなります。
区分表示
営業活動、営業外活動、特別項目などを区分けして表示します。これにより、通常の営業活動による利益か、特殊な事情による一時的な損益かが明確になります。
おわりに
損益計算書は、企業の収益性や収支バランスを確認するための中心的な書類のひとつです。とくに営業利益や当期純利益といった各種の利益指標は、企業の健全性や成長性を見極める重要な情報源となります。
財務諸表の読み方に慣れていくことで、企業活動の実態をより深く理解できるようになります。グループ経営が一般化しているので、連結損益計算書は経済やビジネスを読み解く上で不可欠なものとなっています。