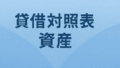貸借対照表(Balance Sheet)は、企業が一定時点において保有している資産、負債、純資産(資本)を一覧で示す財務諸表です。企業の経営状態、すなわち「何をどれだけ持っていて」「どこからその資金を調達しているのか」を一目で確認できる点が特徴です。
この表は、資産と負債+純資産のバランスを取る構成になっており、「企業の財政状態を静止画的に捉えるもの」と言われることもあります。
貸借対照表の構成
貸借対照表は大きく次の3つの区分で構成されます。
- 資産(Assets):現金や建物、売掛金など、企業が保有する価値のあるもの。
- 負債(Liabilities):借入金や買掛金など、将来の支払い義務があるもの。
- 純資産(Net Assets):資産から負債を差し引いたもので、株主資本にあたります。
この3つの関係は「資産 = 負債 + 純資産」という会計上の基本式で成り立っています。
勘定式と報告式
貸借対照表の表示形式には主に2つのスタイルがあります。
| 区分 | 特徴 |
|---|---|
| 勘定式 | 左側に資産、右側に負債と純資産を記載する形式(帳簿のようなスタイル) |
| 報告式 | 上から順に資産→負債→純資産の順に並べる縦型の形式(報告資料向け) |
日本では主に報告式が用いられていますが、企業によっては勘定式も併用されることがあります。
流動項目と固定項目
資産・負債はいずれも、以下のように「流動」と「固定」に分類されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 流動資産・負債 | 1年以内に現金化または決済されるもの(例:現金、売掛金、買掛金) |
| 固定資産・負債 | 1年以上の期間にわたって使用または返済されるもの(例:建物、長期借入金) |
分類の基準には、後述する「正常営業循環基準」と「ワン・イヤー・ルール」があります。
正常営業循環基準とワン・イヤー・ルール
資産や負債を流動・固定に分類する際には、以下の2つの考え方を組み合わせて判断します。
- 正常営業循環基準:企業の通常の営業サイクル内で回収・支払いが完了するものを流動とする。
- ワン・イヤー・ルール:上記以外で1年以内に現金化・決済されるものを流動とする。
このルールによって、取引の性質と期間の両面から分類されます。
流動性配列法と固定性配列法
資産の表示順序にも2つの考え方があります。
| 区分 | 説明 |
|---|---|
| 流動性配列法 | 流動性が高い順(現金 → 売掛金 → 在庫 → 建物)に並べる |
| 固定性配列法 | 固定性が高い順(建物 → 在庫 → 売掛金 → 現金)に並べる |
日本では「流動性配列法」が一般的ですが、国際会計基準では固定性配列法も見られます。
総額主義の原則
貸借対照表は、総額で記載することが基本とされています。
- 資産や負債を相殺せず、原則として個別に記載
- たとえば、売掛金と買掛金を相殺してはいけません
これにより、財務内容の透明性が確保され、実態が正しく伝わるようになっています。
重要性の原則
会計処理では「重要性の原則」も重視されます。これは、
- 企業の財務判断に影響を与える項目のみを記載すればよいという考え方
- 少額の資産をまとめて「備品」として処理するなどの例があります
この原則により、貸借対照表が過度に煩雑にならず、実務的な対応が可能となっています。
連結貸借対照表とは
親会社が子会社を支配している場合、親子会社の資産・負債を合算し、企業グループ全体の財政状態を表す「連結貸借対照表」が作成されます。
-
親会社と子会社間の取引や債権債務は相殺
-
少数株主の持分(非支配株主持分)も表示
このような連結情報は、企業の実態をより正確に反映するため、投資家や金融機関にとって重要な指標となります。
貸借対照表の分析指標
貸借対照表からは以下のような財務指標も導き出されます。
| 指標 | 意味 |
|---|---|
| 流動比率 | 流動資産 ÷ 流動負債 × 100(短期的な支払能力) |
| 自己資本比率 | 純資産 ÷ 総資産 × 100(財務の健全性) |
| 固定比率 | 固定資産 ÷ 自己資本 × 100(長期資金の充当状況) |
これらの指標も合わせて確認すると、企業の安全性や安定性についてより深く理解できるようになります。