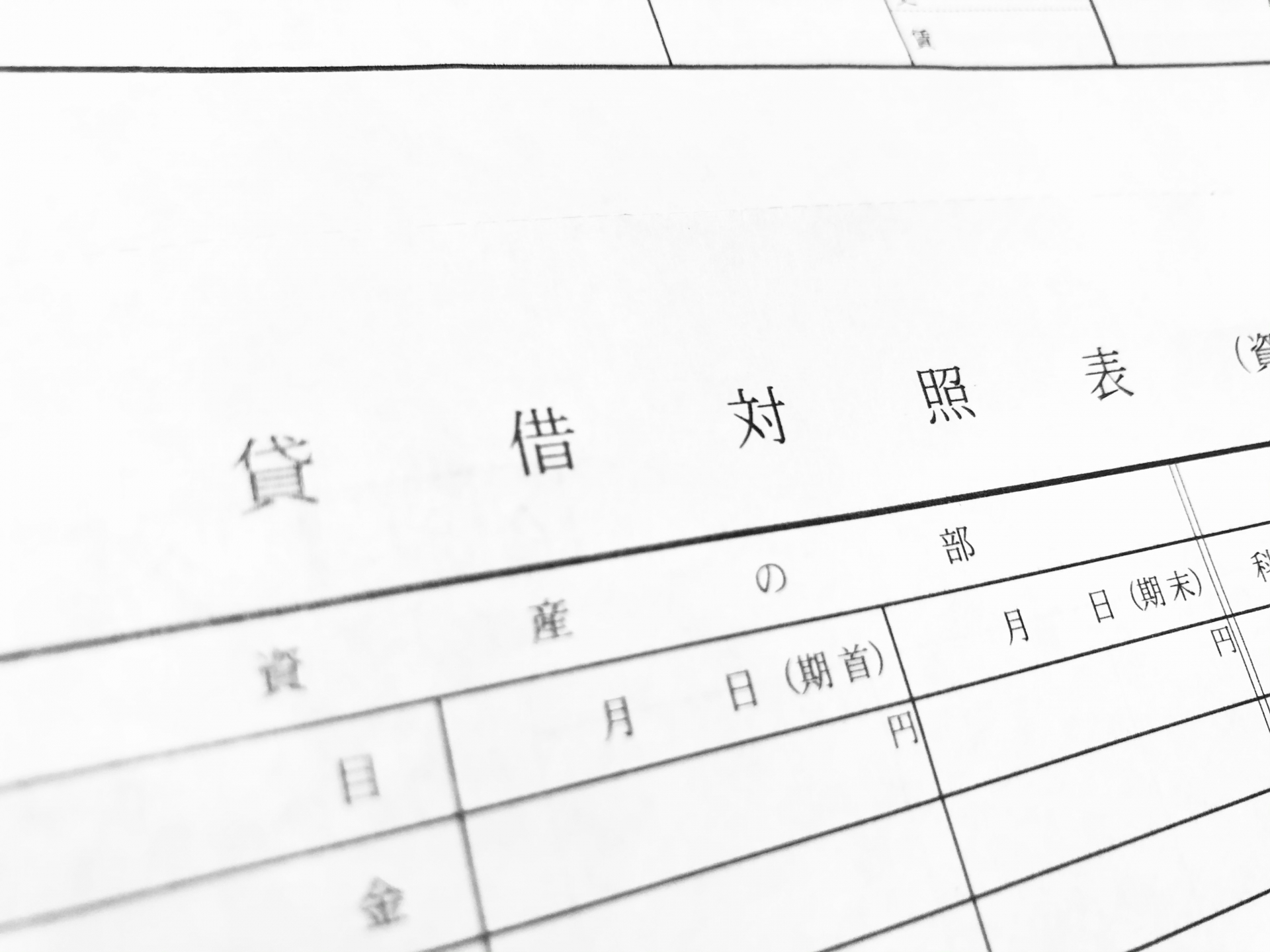商品の流通に欠かせない貨幣には、大きく3つの働きがあります。
- 商品の交換のなかだち
勤労者は労働力を企業に売って賃金という貨幣を得ます。
そしてその貨幣で商品を買うことができます。
労働力と商品の間を、貨幣が取り持つ関係になります。 - 商品の価値をはかる尺度
商品の値打ちをあらわす尺度(ものさし)としてのはたらきをもちます。 - 価値の保存
貨幣は値打ちをそのままで保存でき、貯蓄の手段としてのはたらきをもちます。
※ただし、物価の上昇により貨幣価値が下がる場合もある
その他に、税金などの交換ではなく一方的な支払いの手段としての働きや、資本となって利潤を生むはたらきもします。
貨幣の歴史
貨幣は物々交換の時代に、どんなものとも交換できる物品を決めてからはじまりました。その後、利便性のために金属、紙幣、通貨と形を変えて発達してきました。
物品貨幣
初期の貨幣は、経済エリアごとにどんなものとも交換できる品物でした。
- 生活必需品(塩、布、稲など)
- 装飾品(貝殻、象牙など)
- 生産用具(鋤、家畜など)
ただ、物品だと品質や種類が不揃いだったり、持ち運びが不便だったりといったデメリットがあり、経済エリアが広がっていくにつれて金属貨幣に変わっていきました。
金属貨幣
銅・銀・金などの金属による貨幣です。
- 秤量貨幣:取引のたびに目方を量ったり、品質を調べたりしたもの
- 鋳造貨幣:一定の目方・品質・形に鋳造したもの
といった貨幣があり、物品貨幣に比べて品質が均一で、保存・分割・持ち運びも便利になりました。
ただ金属貨幣も、すり減ったり多額の持ち運びが難しいといったデメリットがあります。
紙幣
貨幣としての値打ちを印刷した紙です。値打ちは国が保証するもので、中央銀行が発行します。
- 兌換紙幣:金・銀と交換できる
- 不換紙幣:金・銀と交換できない
現在は金属貨幣と紙幣が貨幣の主流となっています。
預金通貨
信用経済の発達により、当座預金、普通預金、手形、小切手、電子マネーなども用いられるようになっています。
通貨制度
社会で流通している貨幣を通貨といいます。そして通貨を発行して流通させる仕組みを、通貨制度(貨幣制度)といいます。
現在はどこの国でも、国と中央銀行が通貨の発行を管理して、その通用を保証する管理通貨制度となっています。
※昔は国が保有する金(ゴールド)の保有高だけ貨幣を発行する金本位制度が取られていました。ただ金は採掘量に限りがあり、流通により国内外への移動も激しく安定して保有できない、戦争や恐慌時は紙幣発行量に対し金が不足するなど維持が難しいといったデメリットがあります。そして金と交換できる兌換紙幣は廃止され、不換紙幣が貨幣として発行されるようになりました。